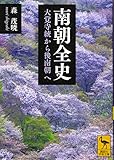銚子電鉄の古めかしく老朽化した車両に揺られ、我々は終点の一つ手前、犬吠の駅に向かって出発した。娘は疲れが出たのか、私の膝に凭れて寝入ってしまった。車内には広告の代わりに、或いは広告を兼ねて、銚子の醤油醸造や漁業の歴史に関する説明が掲示されている。醤油の製法を持ち込んだのも、外川の港湾を整備して漁業の発展を促したのも、遥か遠方の紀州から移り住んだ人々の功業であるらしく、千葉と和歌山との意外な結び付きに就いて蒙を啓かれた。
茶髪を束ねた小柄な女性の車掌が、切符の車内販売や検札、扉の開閉など、複数の業務を担って遽しく走り廻っている。切り詰められた人件費の弊害であろう。銚子電鉄は旅客収入以外の様々な事業、主には話題性を狙った奇妙で滑稽な物販によって経営を維持していると聞いたことがある。駅名と絡めた駄洒落のようなアナウンス(「本銚子」と「本調子」など)が、恐らくは地場の企業と思しき広告主の社名を連呼する。日曜日だからだろう、乗客の過半は観光が目的の様子で、老若男女を問わず、物珍しげに駅舎や車窓越しの景色を眺めている。キャノンの本格的なカメラを携えた妙齢の女性もいる。廃線寸前の傾いた鉄道事業を逆手に取って観光資源として活用するというのは、近年の客寄せの常套であろう。コロナショックが致命傷に帰結しないことを祈る。立派な寺社仏閣に限らず、古びた電車も立派な産業遺産(否、未だ現役である)であり、その歴史的価値は、積み重ねた年輪に応じて高騰していくものである。従って、一日でも長く延命することが重要な意義を有するのだ。何でも若ければ若いほど好ましいとは限らない。
犬吠駅に着いて、地元の巨大醤油会社の名前が入ったベンチに腰掛け、一息吐いた(銚子市内を散策していると「ヒゲタ」と「ヤマサ」の名前が記されたベンチに何度も遭遇する)。本当ならば、犬吠埼のホテルにチェックインする前に「地球の丸く見える丘展望館」へ立ち寄る積りだったのだが、四歳になる娘が筋金入りの横着者で、少しも自分の健脚を使役せずに、父親の腕で運ばれることばかりを要求してくる為に、我々夫婦は疲労の極致に達していて(何故か全く自力で歩行していない娘も疲れていて)、その日は断念することに決めた。とりあえず緩やかな坂道を辿ってホテルまで歩き、太平洋の大海原が見渡せる客室で荷解きと休憩を済ませてから、犬吠埼灯台を見物しに行くことにした。ホテルの駐車場の脇に設けられた足湯で磨耗した筋肉を癒やしてから、駐車場を横切り、叢に覆われた剣呑な近道を通って灯台へ向かう。途次「犬吠テラステラス」という名の真新しい商業施設を物色し、僅かに散り出した糠雨を懸念しながら白亜の灯台へ急ぐ。生憎の天候で景色は薄暗く、濁った海は不吉な印象を見る者に与える。明治七年に竣工し、国の登録有形文化財に指定されている犬吠埼灯台は、極めて細身で小柄な体軀の持ち主で、九十九段の螺旋階段は擦れ違うのも困難なほど窮屈な造作であった。娘は俄然情熱を燃え立たせて自力で階段を登り切った。その反動でホテルまで抱っこを命じられることは必定である。
ホテルに戻り、夕食の時間までは特段の用事もない。私は娘を伴って大浴場へ赴いた。旅行の愉しみは温泉に尽きる。もう少し娘が大きくなれば、一緒に男湯の巨大な浴槽へ浸かることも出来なくなるだろう。露天も含めて複数の浴槽が鎮座する大浴場に娘は終始上機嫌で、熱がることもなく気持ち良いと喜んでいる。塩化物の潤沢な泉質であるらしく、濡れた唇を舐めると塩辛かった。シャワーで念入りに濯いでから、浴衣に着換えて娘の髪を乾かして束ねたり、自分の髭を剃ったり、身嗜みの時間を持った。娘が浴衣の裾を踏んで廊下を歩くのを見兼ねて、番台の女性が一回り小さいサイズの浴衣を用意してくれた。再び更衣室へ引き返して着替えさせると丁度良い。湯気の立つ娘を連れて部屋へ戻り、冷房の効いた室内で寛ぐ。広い窓の向こうには灯台が見え、空が暗むのに合わせて白っぽい光が燈った。闇に浸された海は不気味である。波音ばかりが際立って鼓膜を揺さ振り、波頭が生き物のように暗闇の中で仄白く滲む。沖合には疎らな漁船の灯が見える。鴨川へ旅行したときも同じ感想を持ったが、夜更けの沖合に船を浮かべて働く人々は、恐怖を感じないのだろうか。傍目には、余りに儚い光に見える。到底、太平洋の凄まじい破壊力に抗し得るようには見えない。私は東日本大震災を想起し、東北の沿岸を襲った津波の威力を想像した。自然の怖ろしさは、有史以来未だに克服されていない。今後克服される見通しも立っていない。そう考えると、約百五十年前に築かれた犬吠埼灯台が、今も崩落せずに形を保っているのは信じ難い奇蹟のように思われる。昼夜を問わず劇しい風雨に晒される場所に屹立しながら、消え残った希望のような光を放ち続ける灯台に、孤独な洋上を行き交う船は擬人的な慰藉を見出すのではないだろうか。我々は観念的な抒情に基づいて、豊かな自然を故郷だと言いたがるが、真に故郷と呼べるのは人工的な事物や環境であり、全く人間の手で馴致されていない自然は、如何なる親愛の情も示さぬ邪悪な存在である。
サラダ坊主風土記 「銚子・犬吠埼」 其の一
家族で一泊二日の銚子旅行に出掛けたので、その記録を簡潔に書き留めておく。
新型コロナウイルスの感染拡大以来、人間の移動は制限され、旅客は著しく減少し、東京駅の構内に立地する私の配属先の店舗も、売上の激減に苦しんでいる。今夏の盆休みの新幹線指定席予約は例年の二割ほどに留まり、観光や運輸といった業界は出口の見えない深刻な打撃に苛まれ、恐らく今後、関連する廃業の件数は増え続けるだろう。
我が家では例年、夏季に二泊三日の旅行へ出掛けるのが習いで、昨年は金沢、一昨年は盛岡、その前年は仙台及び松島を旅した。今年はコロナの影響を鑑みて規模と予算を縮小し(県外移動は歓迎されない時勢であるし、今夏の賞与は若干減額だった)、一泊二日で千葉県銚子市へ出掛ける算段を整えた。
政府の打ち出した「Go To Travel」キャンペーンの恩恵で宿泊費は割引となり、例年なら新幹線で移動するところ、今年は在来線特急「しおさい」で一時間半ほどの道程なので、交通費も随分と安上がりで済んだ。難点は、新幹線とは比較にならぬ便数の少なさである。午前八時台の電車を逃がしたら、次は十時台である。それでも、東京駅まで出向くのに比べれば、千葉駅は遥かに近い。私の暮らす幕張から、総武線各駅停車若しくは京成千葉線で十分ほどの距離である。早めに着いてトイレを済ませ、構内のコンビニでおにぎりやサンドイッチを買い込んで、八番線のプラットフォームから総武本線特急「しおさい」に乗り込む。自由席の車両は空席が目立ち、座席四つを占有して、悠然と向い合わせに陣取ることが出来た。
午前八時過ぎに千葉駅を発ち、佐倉・八街・成東・横芝・八日市場・旭・飯岡を経て銚子駅に辿り着いたのが午前九時半過ぎであった。列車を下りると直ぐ眼前に、巨大な醤油樽が写真撮影を待ち侘びるように佇んでいるのに出喰わした。法被を纏った銚子観光協会の老女が妻のスマホで家族の記念写真を撮ってくれた。生憎、随分とブレた仕上がりであったが、その厚意には感謝の言葉しかない。
先ず我々は駅前のロータリーから路線バスに乗り、海沿いの銚子ポートタワーを目指した。千葉市の海浜公園にも、同じくポートタワーと銘打った展望施設がある。千葉のポートタワーに比べると、銚子のそれは背丈が低い。バス停の直ぐ傍には「ウォッセ21」という名称の水産物即売所があり、タワーと連絡通路で接続されている。何れの施設も老朽化が進んでおり、喫煙所に設置されたアイスの自販機は上下が露骨に錆びていた。タワーの上層へ昇る為のエレベーターも、歴史を感じさせる年代物だった。
展望台から眺められる海景は、生憎の曇り空で清々しさを欠いていた。茫洋たる白っぽい太平洋の水平線、防波堤を食い荒らす冷たい波頭、早朝の活況を通り過ぎた後の無人の水産市場。賑わいや輝きとは隔たった、何処か荒涼たる風景だった。娘を抱え上げてテレビ式の望遠鏡を覗いてから、土産物を商う階層へ降りる。四歳の娘が黄色い車のような飛行機のような奇妙な玩具を買ってくれと言い出し、拒んでも大声を張り上げて徹底抗戦も辞さぬ構えである。こういうときは、宥め賺しても厳しく叱っても無益である。後で買ってあげると誤魔化しながら半ば強引にフロアを出て、階下のシーフードレストランで昼食を取った。妻は海鮮丼、私は穴子の天丼、娘は口に合うものがない。後で何か別の食事を手当てせねばなるまい。隣席にはライダーらしい黒の革ジャンの男たちが大人数で陣取り、和やかに食事をしていた。この銚子の海辺は、ツーリングで遊覧するのに適した土地なのだろう。
娘の指名した奇妙な玩具は嵩張るので、何とか言い包めて柔らかい刀の玩具を二本買ってやった。娘は荒ぶる血の持ち主で、戦いごっこが好きなのである。そのふにゃふにゃの剣を持って、地上階のアスファルトの広場で決闘を演じる。娘は加減を知らず、思い切り叩きつけて来るので、ふにゃふにゃでも痛みが走る。余り反撃すると、娘は自分が劣勢であることに屈辱と不安を覚えて機嫌を損ねるので、此方は適度な匙加減を心掛ける必要がある。
水産ポートセンターの敷地を出て、海の見える車道沿いの停留所で銚子駅へ引き返すバスを待った。岸壁に沿って釣り竿が並び、その傍らには海上保安庁の船舶(「つくば」という船名が金文字で艫に記されていた)が停泊している。バスに乗り、銚子駅へ舞い戻ると、JRの自動券売機で銚子電鉄の切符を買った。未だ時間があったので、コンビニで娘の食糧を調達し、ベンチに座って食べさせる。彼女は食べ物に関して保守的な性質の持ち主なので、見慣れないもの、得体の知れないものは口に入れたがらず、旅先ではいつも食事の選択に難渋するのが悩みの種である。
銚子電鉄の乗り場は、JR在来線プラットフォームの突端にあり、suicaの出場処理をする為の端末が置いてあるが、改札は存在しない。日曜日なので、恐らく旅客の九割九分九厘は観光客である。レトロな車両や駅舎を愛でる為に訪れたのだろう。大正年間に設立開業した当時の面影が、鱗粉のように随所へ塗されているのかも知れない。事実、中吊り広告の一枚は、開業当時の宣伝文の復刻であった。
「権威/権力」の例外的統合 森茂暁「南朝全史」
俄かに歴史の勉強を思い立って、無きに等しい知識の培養と底上げを図り、日本史に関する解説書の類を渉猟している。いきなり古典や史書に挑むのは命知らずの蛮勇なので、成る可く分かり易いもの、素人でも辛うじて読みこなせるものを探している。
学生の頃、日本史の授業を受けていた筈なのに、怠惰な私は断片的な記憶を脳裡に散乱させるだけで、歴史的な推移の過程をまともに要約するだけの知識も理解も欠いている。顧みれば、恐らく小学校の頃だと思うが、子供向けに編輯された現代語訳の「平家物語」を読んで、それなりに愉悦を覚えた記憶が残っている。尤も、私はそれを単なる物語の一種と看做して読んだだけで、入り組んだ歴史的背景や経緯を理解していた訳ではない。京都の府立植物園へ、母親の運転する車に揺られて向かう一時間余りの間、後部座席で蒸暑い思いをしながら、以仁王の挙兵だとか、福原遷都だとか、清盛の病死だとか、壇ノ浦の合戦だとか、そういった挿話を啄むように味わったのである。その光景だけが、妙に鮮明に眼裏へ浮かび上がる。
森茂暁氏の『南朝全史』(講談社学術文庫)は、その副題が示す通り、鎌倉時代の後期に生じた皇統の分裂から、鎌倉幕府の瓦解、後醍醐天皇の「建武の新政」を経て、室町幕府の誕生に至る南北朝の乱世を扱った書物で、その眼目は所謂「南朝」の歴史を総体的に浮かび上がらせることに存する。皇族に限っても夥しい数が登場する煩瑣な人名を、その相互的関係と結び付けて記憶することに酷く骨が折れた。複雑に絡み合う「両統迭立」の過程に関する平明な叙述を読んでいる間も、顕れる人物が持明院統と大覚寺統の何れに属するのか咄嗟に分からず、それゆえに文脈の含意を読み損なって解釈が難渋したり屈折したりする。その合間に貴族や僧侶まで割り込んでくると愈々御手上げである。
「南朝全史」の内容から聊か話が逸れるのだが、戦後の坂口安吾が著名な随筆である「堕落論」の中で「天皇」に就いて次のように述べている。
私は天皇制に就ても、極めて日本的な(従って或いは独創的な)政治的作品を見るのである。天皇制は天皇によって生みだされたものではない。天皇は時に自ら陰謀を起したこともあるけれども、概して何もしておらず、その陰謀は常に成功のためしがなく、島流しとなったり、山奥へ逃げたり、そして結局常に政治的理由によってその存立を認められてきた。社会的に忘れた時にすら政治的に担ぎだされてくるのであって、その存立の政治的理由はいわば政治家達の嗅覚によるもので、彼等は日本人の性癖を洞察し、その性癖の中に天皇制を発見していた。それは天皇家に限るものではない。代り得るものならば、孔子家でも釈迦家でもレーニン家でも構わなかった。ただ代り得なかっただけである。
すくなくとも日本の政治家達(貴族や武士)は自己の永遠の隆盛(それは永遠ではなかったが、彼等は永遠を夢みたであろう)を約束する手段として絶対君主の必要を嗅ぎつけていた。平安時代の藤原氏は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、自分が天皇の下位であるのを疑りもしなかったし、迷惑にも思っていなかった。天皇の存在によって御家騒動の処理をやり、弟は兄をやりこめ、兄は父をやっつける。彼等は本能的な実質主義者であり、自分の一生が愉しければ良かったし、そのくせ朝儀を盛大にして天皇を拝賀する奇妙な形式が大好きで、満足していた。天皇を拝むことが、自分自身の威厳を示し、又、自ら威厳を感じる手段でもあったのである。(「堕落論」『日本文化私観』講談社文芸文庫 pp.201-202)
坂口安吾の慧眼と博識が冴え渡る文章である。事実、藤原氏の摂関政治や、征夷大将軍による幕政などを鑑みれば明らかなように、日本史の様々な場面に見出されるのは「権威の形骸化」若しくは「権威と権力の乖離」という力学的現象であり、もっと卑俗な表現を用いるなら「本音と建前の使い分け」である。或いは極端な形式主義と看做しても恐らく大過はない。紛れもない究極の「権威」である「天皇」を推戴しつつ、その「権威」とは別個に存在する臣民の有力者が政治的実権を掌握し、水面下を暗躍して素知らぬ顔で物事を動かしていくという政治的様態は、例えば源氏の嫡流が途絶した後の「親王将軍」と「執権」との関係性にも明瞭に示されている。「権力」の中枢が、絶えず「権威」の物蔭に忍んで隠匿されるというのは、日本史の常道である。
こうした傾向を踏まえて眺めたとき、所謂「建武の新政」という改革を取り仕切った後醍醐天皇は、正に「異形の王権」(網野善彦)と呼ぶに相応しい人物である。森氏の叙述に従えば、後醍醐は「綸旨」の関わる分野を拡張し、軍事や恩賞を踏み込んで直轄し、裁判の処理にも自ら携るなど、積極的な「親政」を推進した異例の天皇であるということになる。言い換えれば、後醍醐において日本の政治的な「権威」と「権力」の合体が半ば腕尽くで実現されたのである。持明院統及び大覚寺統の間で争われた皇位を巡る鞘当ては代々、鎌倉幕府の意向と密接に結び付いた形で演じられてきた。後醍醐の幕府に対する敵対的な野心が、直接には大覚寺統の劣勢という時流や、大覚寺統の内紛に基づいて喚起されたのだとしても、重ねて蹶起を企てた後醍醐の独裁に対する信念は、そのような旧来の伝統そのものを破壊することに、そもそも強固な関心を寄せていたように思われる。
「権威」と「権力」を重ね合わせ、一体化することが、天皇の抱懐する野望の原則であるとするならば、両者を分裂させ、謂わば「権威」から「権力」だけを選択的に略取することは、藤原氏や将軍家など、人臣の頂点に位置する公卿や棟梁たちの有する野心の中核である。単純化して言えば、絶対的な王権としての天皇と、行政や司法に関する諸々の実務に携わる高位の人臣との間で演じる「権力」の苛烈な争奪が、日本史を貫き動かす巨大な伝統的活力なのである。
私は外国の歴史に関して日本史以上に無学文盲の輩であるから、この「権威/権力」の二重性という現象が本邦に固有の特徴であるのか、世界的に広く見られる傾向なのか、判断を下すことが出来ない。何れにせよ、天皇の帯びる絶対的な「権威」の正統性は明瞭に担保したまま、実質的な「権力」を骨抜きにして、臣下の筆頭が国政の実権を恣にするという構図は、年代を問わず、日本史において幾度も繰り返し発生している。「朝廷/幕府」の二重性は、鎌倉から幕末に至るまで、束の間の断絶を挟みながら数百年の長きに亘って維持されてきた。
後醍醐天皇は、幕府による容喙を排除して(その直接的な引鉄が、自らの皇位の脆弱性に由来したのだとしても)天皇による独裁的な親政を企図した。広範な分野に及ぶ政務の大半を自ら発する「綸旨」で決裁したのも、肥大した人臣による親政の歪曲や妨礙を警戒した為ではないかと思われる。それは国家における「権威/権力」の二重性を解消し、統合しようとする政治的衝迫の具体的表現である。但し、後醍醐の描いた野望は、日本史において極めて例外的な夢想であり、その実現は儚い寿命しか与えられなかった。建武の新政は瞬く間に瓦解し、足利尊氏による室町幕府の樹立が、旧来の「権威/権力」の二重性という国家的構造を恢復させた。つまり日本においては「権威/権力」の分裂こそ、国政における標準的状態であると言えるのかも知れない。実質を持たない虚飾、形式的な権威、そういったものを忠実に珍重しながら、具体的な行動の次元では、その崇高な権威を蹂躙して恥じない、そういう分裂的な心性が、本邦の歴史を通じて鮮明に浮かび上がるのである。天皇を権威に据えて征夷大将軍が実権を握り、征夷大将軍を権威に据えて執権が実権を握るという鎌倉期の入れ子構造、この無限の偏倚は、単なる偶発的な現象のようには思われない。絶えず「権力」を形骸化させながら、その残骸としての「権威」の外皮は決して廃絶しないという定型的な構図は、日本社会に内在する根深い傾向、或いは「宿痾」のように見える。こうした消息を指して、丸山眞男は「無責任の体系」という表現を持ち出したのだろうか。
Cahier(「作品」の歴史的条件)
*「事実は小説より奇なり」(Truth is stranger than fiction)と英国の詩人バイロンは言った。一般に小説家は様々な経験や伝聞や私見を混ぜ合わせて、虚構の物語を作り出す。その原料が現実の世界、我々の肉体を囲繞する世界から採取されるものであることは言うまでもない。作者が如何なる現実を作品の原料に選択するか、そして採取した原料に如何なる調理を施すか、こうした個別的判断の集積が、作者の個性や風儀を生み出す。
作品が作者の内部から発露された純然たる独立的な個体であると看做すのは、芸術の自律性と優越に対する信仰に基づく考え方である。そのような仮定を踏まえて、作品の内在的な論理を解釈するのも一つの理解の手法には違いないが、実際問題として、作者と作品が限定された社会的環境から超越的な自由を手に入れることは不可能であろう。そもそも小説が他者と共有される社会的言語を通じて表出されるものである限り、小説の内在的論理が社会的環境から切断された普遍的なアイデンティティを保ち得る筈はなく、作者と作品が常に社会的境遇や歴史的条件との流動的な関係の場に置かれていることは明白な事実である。それゆえに作者と作品に対する評価は、時代の変遷や環境の変化に伴って揺れ動くのである。或る作品が重要な古典的価値を認められるのは、その古典的価値が作品の内部に普遍的な仕方で、謂わばプラトンの論じる「イデア」のような形態で内在しているからではない。その作品と、その作品を評価する社会的な現実との関係性が、綜合的な評価を定めるのである。
つまり「永遠の古典」という考え方は成り立たないのであり、その都度「永遠の古典と看做された」という歴史的事実が形成されるというだけに過ぎない。時代の変化によって忘れ去られていた作家が再評価され、劇的な復権を遂げ得るのは、その作品に内在する普遍的な生命力の耀きといった抽象的理由に由来する現象ではなく、その作品と社会的現実との関係性の変動の帰結である。
言い換えれば、小説作品を読解するに当たって、その作品と社会的事実との関係性を把握することは、読解の精度を高める有効な方法であると考えることが出来る。それは必ずしも個別的な作品を社会的現実の単純な隠喩に還元するという意味ではない。独創性の帰結と信じられている要素が往々にして歴史的な構造の帰結であることを踏まえて、読書に励むべきだと私は思うのである。
例えば安部公房の長篇小説『けものたちは故郷をめざす』(新潮文庫/岩波文庫)は、満州で生まれ育った作者の個人史的な経験を原料として用いている。無論、あの作品の固有性は、歴史的な事実の集積に必ずしも還元されないが、作中に示された固有の考えや感受性が、満州の歴史的条件と無関係に形成されたものであると看做すのは謬見であると思う。無論、作品の歴史的条件など興味はない、作品そのものの内部に滞在している個々の瞬間の経験だけが決定的に重要なのだという考え方を批難する積りはない。それが一つの純粋な快楽の方式であることも事実だろう。だが、少なくとも私個人に関して言えば、そういうストイックな方針だけでは物足りないのである。
作品は、作者と社会的現実との関係性の帰結である。その関係性に与えられた表現が作品と呼ばれる。そして作者の創造に対する衝迫や情熱が、四囲の現実に触発されることによって生じることは明瞭な事実である。例えば三島由紀夫の傑作『金閣寺』(新潮文庫)の世界を、作者の個人史的経験から完全に切り離して捉えることは無意味である。昭和元年に生まれ、二十歳で終戦を迎え、世界の劇的な変貌に直面した三島の個人史的経験が、あの作品の基底に脈々たる流れを築いていることは明瞭である。空襲による滅亡の予感や、敗戦を契機として復活した無限の日常性に対する呪詛など、こうした要素が三島の生きた時代の歴史的条件と密接に結び付いていることは確実である。作品が歴史的産物であること、これは疑いようのない堅固な真理だ。三島がラディゲの作品に熱狂したのは、例えば『肉体の悪魔』(光文社古典新訳文庫)が、戦争とロマンティシズムの奇妙な融合を描いているからではないか。そうだとしたら、そこにはやはり歴史的条件が関与しているのである。戦争の終わりと禁じられた恋愛の終わりが同期する世界、つまり愛することが滅亡することと濃密な相関性を有しているような世界、こうした三島的なロマンティシズムの世界像が、三島自身の個人史的経験に由来するものであるならば、作品が歴史的条件の帰結であり産物であることに、我々は同意せざるを得ないのではないか。
Cahier(混迷の時代)
*世界は混迷の時代を迎えている。無論、混迷というものが一切存在しない時代は古今東西を通じて一度もなかったに違いないが、新型コロナウイルスの世界的な蔓延という不測の事態に蝕まれて、従来の常識や秩序や手法が音を立てて瓦解し、未来に関する見通しは不透明を極めている。日本に関して言えば、憲政史上最長の在任を誇る安倍晋三内閣総理大臣の唐突な辞意表明があり、国内総生産は戦後最悪と言われる下落を示し、郵政・鉄道・航空などの社会的なインフラに関わる大企業が悲惨な窮状に追い込まれている。長く高止まりしていた有効求人倍率は低下し、失業率は急速な悪化の途上にあり、少子高齢化及び人口減少の流れに歯止めは掛からず、2019年度の出生数は1899年の調査開始以来最低の86万5千人に留まった。
何もかもが急速な変貌の徴候を明示している。コロナの蔓延が強いる社会的な意識の変革は不可逆的なものであると一般に考えられている。特にコロナの影響は、社会における特定の階層に限って波及するものではなく、この強制的な変化と無縁でいられる人間は何処にもいない。誰もが「混迷」という時代的な宿命に犯されて意識や行動の変革を余儀なくされている。
歴史に関する勉強を始めようと俄かに思い立った背景には、こうした現実の劇的な変動が関与しているように感じられる。この数年、私は主に三島由紀夫の小説を耽読し、最近は安部公房に切り替えて、その奇想に充ちた寓話的な虚構の世界を堪能していた。しかし定期的に訪れる、もどかしいような不安に遮られて、私は安部公房の書物を閉じた。主観的な絵空事に涵って、彼是と思考を巡らせることに不穏な虚しさを覚えたのだ。
以前にも同様の症状は起きた。三島由紀夫の小説を集中的に繙読していた昨年の春先に、虚構の世界に溺れている自分自身の姿に、或いは生活に物足りなさと飢渇を覚え、もっと現実的な知識を学び、摂取すべきではないかという考えに取り憑かれたのだ。そのとき、私が小説を捨て去って取り縋ったのは、古代ローマの政治家セネカの遺した書簡体の随想や、イギリスの哲学者バートランド・ラッセルの著した「幸福論」などであった。要するに「思想」や「哲学」と呼ばれる領域へ分け入って、己の無智と狭量を癒やそうと企てたのである。それでエピクロスやプラトンなど、主には古代ギリシアの古典を中心に読書を進めていったのだが(西洋の歴史的名著を読み始めると、プラトンの対話篇に関する知識がなければ理解し難い箇所が夥しいことに気付いたのだ)、段々と荷が重くなってきた。
哲学的な認識や学説は、厳密な論理による支えを鉄則としているが、その学説の総てを純然たる客観的事実として認めることは困難である。例えば、プラトンの「イデア」や「アナムネーシス」といった概念が、一個の厳密な事実であると断定することは不可能に等しい。或る偉大な思惟の様式を学ぶという意味では有益だが、その思惟の様式が客観的な事実を証明する訳ではないという印象は、私を混乱させた。つまり、哲学の世界というのは百家争鳴で、どの考えが正しくて、どの考えが間違っているのか、そもそも理非を断ずる根拠が奈辺にあるのか、よく分からなくなって疲弊してしまったのである。
もっと言えば、或る哲学者の提示した独創的な思想が、全くの虚無から創造されることは有り得ず、そこには必ず生身の哲学者が属した社会や時代の強力な影響が関与している。つまり、或る人間の示した考えの理非を、純粋に普遍的な「真理」の規矩に従って判定することは原理的に不可能なのである。例えばプラトンの信奉する「真理」とは、そのような普遍的で絶対的な「正しさ」を意味しているが、そもそも普遍的な「真理」が確乎として存在するという揺るぎない確信自体が、プラトンという生身の人間が置かれた歴史的な条件や境遇の帰結であるとするならば、果たして彼の学説の正当性を純粋なる「真理」の次元で捉えることが出来るのだろうか。
こうした考え方が「相対主義」(relativism)に傾斜していることは弁えているが、何も私は何処にも普遍的な「真理」など存在せず、総ては主観的な幻想に過ぎないと、反動的な口調で申し立てたいと考えている訳ではない。ただプラトンの考えている諸々のアイディアが正しいか否かは「真理」の次元に属する問題であり、従って様々な判定が可能であるが、少なくともプラトンがそのような考え方を懐き、社会に向かって表明したということは「事実」の次元に属する問題であると言えるだろう。附言すれば「事実」の正しさも「真理」と同じく一律に定め得る問題ではないし、そもそも「事実とは何か」という難問に取り組むのが哲学者の本領であるとも言えるのだが、何れにせよ「事実」から出発するのが合理的ではないかという考えに私は到達した次第である。
「歴史」は「事実」の総体であり、そこから如何なる考えを引き出すかは十人十色であるが、少なくとも「事実であると認められた事実」に関しては、便宜的に正しいものであると看做すことが可能である。そもそもプラトンやアリストテレス自身、自らの学説を説明するに当たっては、しばしば歴史的な事例を引いている。プラトンの考えに基づいて自分の考えを紡ぎ出すのも大いに結構だが、どうせなら彼らと対等に、同一の次元に属する「事実」と向き合って自分自身の頭で考えてみる方が合理的ではないかと思われる。無論、歴史的な事実が既に主観的な編輯の過程を経由していることは言い古された警告であるが、相互に矛盾する様々な史料を照らし合わせて妥当な推論を展開し、以て唯一の「事実」に至ろうとする専門的な努力が、無数の先賢によって試みられてきたこともまた事実である。「歴史」に学ぶということは「事実」に学ぶことと同義である。それは特定の思潮や学説に基づいて、世界を恣意的に切り取るような態度に附随する害悪を浄化する一助となる。
話は思想や哲学に限らず、文学も同様である。諸々の芸術的な作品は恰かも外界から自立した普遍的で固有な小宇宙であるかのように遇されるのが通例であるが、無論、個別的な作品も、生身の作者を通じて創出されたものである以上、諸々の歴史的条件の制約を蒙っていることは明瞭である。思想や芸術を内在的に捉えるならば、我々はそれを生み出した人々の内面に潜入する以外に、理解の方途を持ち得ない。そして内在的な共振の方法を通じて理解された思想は、絶対的な「真理」のように鳴り響いて我々の精神を眩惑する。しかし、それを歴史的な事実の断片として捉えるならば、我々は固定的な思惟の様式に拘束される危険を、少なくとも部分的には免かれ得る。「事実」は常に外在的で公共的なものであり、個人による恣意的な私有を受け付けない。つまり、私は他人の主観の内部へ移住するような読書に嫌気が差したのだろう。それでは自分の視野が適切な広がりを確保し得ないように感じられたのだろう。とりあえず今は森茂暁氏の著した『南朝全史』(講談社学術文庫)という書物を読み進めている。客観的な事実の集積を通じて、自分自身の知識や思考のレヴェルを深め、高めていきたいと思う。
Cahier(疫病の年の覚書)
*新型コロナウイルスの感染爆発の第二波が峠を越えたと言われているが、恐らくは冬が来るまでに第三のピークが襲来するのだろうし、経済の悪化、雇用の悪化、消費の悪化は相変わらずで、何処まで景気が没落するのか知れたものではない。緩やかな恢復の徴候が垣間見えたとしても、感染が再燃して日々の報道が陰気な色彩を帯びれば途端に経済が停滞することは確実である。こういう一進一退の攻防は、コロナウイルスが単なる軽度の風邪ぐらいに弱毒化し、ワクチンや特効薬が開発され、我々の生活の親しい伴侶として認められるようにならない限り、完全な決着には至らないのだろうと思われる。
私は緊急事態宣言が明けたタイミングで東京駅の構内にある店舗へ異動した。本来ならば世界的にも屈指の利用客数を誇る東京駅は、県外移動の自粛とテレワークの拡大に挟み撃ちされて青息吐息の大不況である。昨年までは全国随一の売上高を誇っていた私の配属先も、前年比で測れば寧ろ全国最底辺の低空飛行を華麗に演じている。目下の私の使命と責務は、かつて指折りの収益を謳歌していた店舗の黒字化という、何とも悲痛な命題に集約されている。
*小売業の現場で働く私には聊か縁遠い話だが、世の中はテレワーク推進の大合唱で、企業によっては賃料の高いオフィスを引き払ったり、通勤手当を廃止したり、単身赴任の辞令を解除したりして、感染リスクの低減と合わせ技で企業経営の合理化を推し進めている。人や物の移動が国家の号令に基づいて遮断されたり抑制されたりしているのだから、実体経済の悲惨な停滞は避け難い。しかも、コロナウイルスの蔓延は国際的な普遍性を備えた現象であるから、この地球上で商売を営む限り、何処にも逃げ場は存在しない。何処の企業も売上に大打撃を蒙り、経費の削減に躍起である。テレワークの推進に便乗して賃料や通勤手当などの固定費の削減を一挙に推し進めるのは賢明な判断であると言えるだろう。労働者の側でも、満員の通勤電車に週五日も揺られなければならない苛酷な生活の負担から解き放たれるのだから、有難い話ではあるだろう。だが、薔薇色の未来を安易に信じ込むのは迂闊である。物事には必ず光と闇がある。
*「出社」或いは「通勤」という労働の条件を解除した場合、如何なる風景が広がるのか。先ず日々定められたオフィスへ物理的に移動する必要がないので、公共交通機関を利用したり自動車を走らせたりすることに関わる諸々の経費が消滅する。通勤手当の廃止は、その端的な帰結である。通勤が如何に不毛な時間的空費であるかということは、これまで散々に論じられてきた社会的問題であるから、その意味では、コロナの影響に基づくテレワークの拡大は貴重な恩恵であると言えるだろう。ただ、あらゆる企業にとって、この傾向が経営合理化の抜本的な契機に繋がるとは言えない。鉄道会社、航空会社、自動車産業など、人間の移動に関連する企業にとって、テレワークは業績に対する逆風を意味する。旅行代理店、宿泊施設、駅に附随した商業施設、燃油の元売りや小売りなども深刻な悪影響を蒙る。他方、人間が動けないので、荷物の方に動いてもらおうという流れは生まれるだろうから、旅客輸送に比べれば貨物輸送の蒙る打撃は軽微で済むだろう。無論、企業活動そのものの全般的な沈滞が、貨物の総量自体を減少へ追い込むので、全くの無傷という訳にはいかない。
*テレワークの推進が、人間の移動自粛と反比例するように、情報通信の拡大を要求することは自然な帰結である。現に「Zoom」の売上高は前年比460%に達しているらしい。家電量販店ではパソコンが飛ぶように売れていると聞くし、自宅で業務を遂行する為に必要な付帯的設備、つまり家具や家電の売れ行きも良くなっているだろう。
*テレワークの推進は「居住の自由」を生み出す。通勤可能な距離という物質的条件が消滅すれば、何処に住んでいても業務に差し支えることはない。従って通勤通学の利便性を理由とした都市部への集住に対する関心は薄れ、コロナ感染のリスクに対する考慮も相俟って、郊外や地方への移住が促進される。しかし、それが直ちに地方の「創生」を齎すとは言えないだろう。地方に暮らしていても、業務の内容や目的が都心に結び付いているのならば、その人間の労働が地域社会への貢献に帰結するとは限らないことになる。また、テレワークの推進が「居住地」に基づく労働者の選別を排除するならば、その労働者は人材同士の熾烈な国際的競争に巻き込まれる虞が高い。無論、それを危惧するかどうかは、当人の資質や価値観によって異なる。
*テレワークの推進は、他者の存在を電子化=情報化する。貨幣がデジタルな数値に置き換えられるように、上司や部下や同僚は、電子的な情報に置き換えられる。同じ時間を通信によって共有することは出来るが、同じ空間を共有することはない。勿論、抽象的な「場所」を分かち合うことは出来るが、それを物理的空間の共有と同一視し得るかどうかは頗る疑わしい。電子的な繋がりしか持ち得ない相手が、自分と同じ生身の人間であることを実感として認識し得るかどうか、懸念が残る。SNSを通じた他者への陰惨な誹謗中傷の事例を鑑みれば、余り楽観視すべきではないという判断が導かれる。
*テレワークの推進は、他者との「社会的距離」(social distance)を拡大すると共に「心理的距離」(psychological distance)をも拡大する。他者と接触し、親密な関係を持つこと自体が、公序良俗に反するかのように看做される危険がある。確かに遠距離の通信技術が、他者との間に社会的回路を開拓する為の有用な手段であることは論を俟たない。また、その技術的な品質が長足の進歩を遂げていることも事実である。けれども、テレワークが他者との無用な接触を避けるという趣旨を含んでいる以上、通信技術の活用が一種の「迂回」であることは否み難い。テレワークにおける通信は、物理的な距離を超克する手段であると同時に、物理的な距離を維持する為の装置としての側面も併せ持っている。それは実体としての他者を、電子的な他者に置き換えることによって無害化し、消毒する手続きであるとも言い得るのだ。
*テレワークの推進は「職住一体化」を、つまり「労働」と「生活」との境界線を掠れさせ、溶解させる。少なくとも雇用契約で縛られた被用者である以上、両者の融合は「生活」への「労働」の侵入という形式を取らざるを得ない。一日の時間の裡、何処までが「労働」で何処までが「生活」なのか、その線引きが不明瞭なものになるとすれば、総ての「生活」の時間が「労働」への待機という性質を附加されることになりかねない。言い換えれば、あらゆる「生活」の時間が潜在的な「労働」として心理的に位置付けられかねない。それは「労働」による「生活」の内在的支配の強化を意味するだろう。我々の「生活」の随所に「労働」が不可視のウイルスのように混入するのだ。勤勉な労働者ほど、この「感染症」に対する免疫は弱体化せざるを得ない。状況を逆手に取って「怠業」に励めるならば、寧ろテレワークの推進は「労働」に対する「生活」の勝利乃至優越を意味するかも知れないが、そのような叛逆が社会的道徳に反するものとして指弾されることは概ね確実である。
*生涯未婚率が上昇を続ける現代の日本社会において、人々が配偶者と巡り逢う環境として最も巨大な比率を占めるのは「職場」であるらしい。その「職場」がテレワークを通じて解体されれば、各種のハラスメントが起こる確率は下がるだろうが、同時に親密な関係の構築される可能性も低下するだろう。つまり、テレワークの推進は更なる未婚化、更なる少子化、更なる人口減少を齎す決定的な機運となるかも知れない。遠距離恋愛の困難に就いては誰もが知るところである。画面越しの電子的な他者を愛することが容易であるとは思えない。
*テレワークの推進は、生身の他者や物理的な現実に対する飢渇を煽るだろう。職住一体化とテレワークの拡大で、我々の生活の範囲は狭まる。そもそも移動自粛の必要に迫られて生じた変化なのだから当然である。我々は愛する人の言葉を重んじるが、同時にその肉体や行動も重んじる。電子化された他者の映像や音声は、或る写実的な言葉である。言葉も大事だが、我々は言葉だけでは充たされない。我々は言葉の彼方に対する根強い憧憬や欲望を捨てられない。我々は、記号ではない。我々は、ヒエログリフではない。
ウイルスに殺された総理
内閣総理大臣安倍晋三氏が持病の再発の為に職を辞するという。コロナ対策は世間の評価を得られず、念願の憲法改正も東京オリンピックの立会いも道半ば、北朝鮮拉致問題も北方領土問題も進捗せず、御本人は悔しさも未練も大いに募るだろうが、それでも再発の発覚から早期に辞職の決断に踏み切ったのは余程病状が重篤なのだろうと推測される。
途端に世間では、憲政史上最長の長期政権を率いた独裁的な首相を慰労しようという感傷的なムードが氾濫を始めた。内閣支持率は急落し、例えば「アベノマスク」や「Go To Travel キャンペーン」など、新型コロナウイルス関連の政治的対策は軒並み世論から仮借無い悪罵を投げ付けられているというのに、病気ゆえの避け難い降板が決まった途端に同情票が集まるのは奇妙というか、余りに冷静な理智を欠いた趨勢であるように思われる。無論、重篤な持病に苦しみながら、内閣総理大臣の重責を担い続けたという事実は、心からの崇敬に値する勤勉さであると言えるだろう。だが、その真摯で超人的な勤勉さを理由に、財務省の官吏を自殺にまで追い込んだ公文書改竄の問題などが免責されて差し支えないという訳にはいかない。身内に便宜を図り、官僚を隷属させ、無責任な答弁で国会の権威を蔑ろにする長期政権の姿が、独裁による腐敗の典型的な症例であることは明白な事実であるように思われるし、そう考えるならば、安易に「お疲れ様でした」という慰労の喝采を送って感傷に浸るのは軽率な選択であるように思われる。長期政権による腐敗、独裁君主による専横を防ぐ為にデモクラシーという政体は存在し、特に日本の場合は、戦時下の軍国主義的なファシズムの暴走が国家滅亡の危機を招いたという生々しい反省(未だ太平洋戦争の惨劇から一世紀も経っていない。「黒い雨訴訟」すら最終的な決着を見ていない)ゆえに、戦後民主主義に対する信頼は根強いものであった筈だ。「アベノミクス」による景気回復、株価の上昇も、今後どういう反動的な負債を齎すことになるか分からない。少なくとも、目下蔓延しているコロナウイルスによる経済への深刻な打撃を直ちに解決する術は、経済に強い安倍総理と雖も持ち合わせてはおられないだろう。
コロナの影響で日本の経済が急激な悪化(戦後最悪の国内総生産成長率を記録した)に陥ったのは全く総理の責任ではない。矢継ぎ早に決定され実施された諸々のコロナウイルス対策が、事態の劇的な改善を示さないとしても、それゆえに総理の能力を批判するのは余りに酷薄な仕打ちである。未曾有の事態に際会して右往左往しているのは総理だけではなく、日本国民全員が同類である筈だ。ただ「アベノマスク」という如何にも的外れな愚策(その経費で定額給付金を増額すればいいと国民の九割九分九厘が考えたのではないだろうか?)の印象もあり、安倍政権のコロナ対応は迷走を極めているという悪評が立ち、結果として内閣支持率の急落を招いたのではないかと思われる。但し、安倍政権の施策に不満を覚えている人々にしても、それでは対案として如何なる方途が有効なのか教えてくれと言われたら、確信と論拠を伴って答えられる人は皆無に等しいのではないか。
好景気の拡大を後ろ盾に強権を発揮し、規則を捻じ曲げ、身内を優遇するという安倍政権の常套は、コロナウイルスという微細な宿敵の登場によって一挙に瓦解を強いられた。経済は急激な停滞を強いられ、医療は逼迫し(昨年十月、政府の経済財政諮問会議の席上、全国の病床数を十三万床削減すべきであるという提言が討議されている)、内閣支持率は急落した。雇用が安定し、消費が活況を呈している間は、少なくともその恩恵に与っている人々は、特段の政治的不満を持つことなく、我が世の春を謳歌していただろう。格差社会に苦しめられ、貧しい生活を強いられている人々の声は抑圧されていただろう。しかし経済が破綻し、生活の儘ならない人々が増えれば、政治的不満は高まり、人心は荒み、時の政権は手頃な八つ当たりの標的に選ばれるだろう。恐らく総理はコロナ蔓延以後、今までの政治的手法、考え方、価値観が何もかも通用しなくなる現実に、絶望的な感情を懐いたのではないか。持病の再発も、その感覚に拍車を掛けただろう。コロナによる経済の停滞は今のところ出口が見えない。安倍政権自身が「地域医療構想」の御題目の下に進めた社会保障費削減政策の影響もあり、脆弱になった医療はコロナの蔓延で青息吐息の危殆に追い込まれている。医療への負担を軽減することを考えれば、経済活動の抑制は避け難い。医療と経済の共存共栄という「コロナの時代」の最重要課題は、安倍政権自身が蒔いた種によって、実現の困難の度合を高めている。そうした現実を踏まえながら、持病を抱えて自民党総裁四選という強権的な未来を切り拓く気力は、流石に不撓不屈の総理も持ち合わせておられなかったのではないかと思われる。
戦後の日本で最も独裁的な政治家の退場を、俄かに巻き起こった束の間のリリシズムに引き摺られて慰労するのは確かに美しい心情であるかも知れず、生身の安倍氏が眼の前にいらっしゃったら私も間違いなく媚びを売って「お疲れ様でした」と頭を下げること請け合いなのだが、コロナウイルスが齎した社会の変動と生活の窮迫は何も解決していない以上、そういう感傷で時間を空費するのは如何なものかとも思うのである。安倍政権の終幕は確かに一つの時代の終焉を示唆しているが、困難な社会的現実は聊かも終焉していない。緊急事態宣言明けに配属されたばかりの私の新たな職場の売上は、コロナの影響で前年の二割弱に留まっている。普通なら首を吊りたくなるような数字だ。そんな私に、道半ばで退場する総理の老いた背中を慰労する余裕などない。全く、本当にどうすりゃいいって言うのさ。憎むべきは総理ではなく、コロナウイルスなんだけどさ。でも人間が本当に憎み得るのは同類である人間だけだから、きっと無益な八つ当たりも流行るのだろう。総理、お疲れ様でした。ゆっくり静養して下さい。