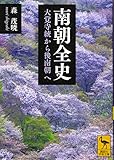俄かに歴史の勉強を思い立って、無きに等しい知識の培養と底上げを図り、日本史に関する解説書の類を渉猟している。いきなり古典や史書に挑むのは命知らずの蛮勇なので、成る可く分かり易いもの、素人でも辛うじて読みこなせるものを探している。
学生の頃、日本史の授業を受けていた筈なのに、怠惰な私は断片的な記憶を脳裡に散乱させるだけで、歴史的な推移の過程をまともに要約するだけの知識も理解も欠いている。顧みれば、恐らく小学校の頃だと思うが、子供向けに編輯された現代語訳の「平家物語」を読んで、それなりに愉悦を覚えた記憶が残っている。尤も、私はそれを単なる物語の一種と看做して読んだだけで、入り組んだ歴史的背景や経緯を理解していた訳ではない。京都の府立植物園へ、母親の運転する車に揺られて向かう一時間余りの間、後部座席で蒸暑い思いをしながら、以仁王の挙兵だとか、福原遷都だとか、清盛の病死だとか、壇ノ浦の合戦だとか、そういった挿話を啄むように味わったのである。その光景だけが、妙に鮮明に眼裏へ浮かび上がる。
森茂暁氏の『南朝全史』(講談社学術文庫)は、その副題が示す通り、鎌倉時代の後期に生じた皇統の分裂から、鎌倉幕府の瓦解、後醍醐天皇の「建武の新政」を経て、室町幕府の誕生に至る南北朝の乱世を扱った書物で、その眼目は所謂「南朝」の歴史を総体的に浮かび上がらせることに存する。皇族に限っても夥しい数が登場する煩瑣な人名を、その相互的関係と結び付けて記憶することに酷く骨が折れた。複雑に絡み合う「両統迭立」の過程に関する平明な叙述を読んでいる間も、顕れる人物が持明院統と大覚寺統の何れに属するのか咄嗟に分からず、それゆえに文脈の含意を読み損なって解釈が難渋したり屈折したりする。その合間に貴族や僧侶まで割り込んでくると愈々御手上げである。
「南朝全史」の内容から聊か話が逸れるのだが、戦後の坂口安吾が著名な随筆である「堕落論」の中で「天皇」に就いて次のように述べている。
私は天皇制に就ても、極めて日本的な(従って或いは独創的な)政治的作品を見るのである。天皇制は天皇によって生みだされたものではない。天皇は時に自ら陰謀を起したこともあるけれども、概して何もしておらず、その陰謀は常に成功のためしがなく、島流しとなったり、山奥へ逃げたり、そして結局常に政治的理由によってその存立を認められてきた。社会的に忘れた時にすら政治的に担ぎだされてくるのであって、その存立の政治的理由はいわば政治家達の嗅覚によるもので、彼等は日本人の性癖を洞察し、その性癖の中に天皇制を発見していた。それは天皇家に限るものではない。代り得るものならば、孔子家でも釈迦家でもレーニン家でも構わなかった。ただ代り得なかっただけである。
すくなくとも日本の政治家達(貴族や武士)は自己の永遠の隆盛(それは永遠ではなかったが、彼等は永遠を夢みたであろう)を約束する手段として絶対君主の必要を嗅ぎつけていた。平安時代の藤原氏は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、自分が天皇の下位であるのを疑りもしなかったし、迷惑にも思っていなかった。天皇の存在によって御家騒動の処理をやり、弟は兄をやりこめ、兄は父をやっつける。彼等は本能的な実質主義者であり、自分の一生が愉しければ良かったし、そのくせ朝儀を盛大にして天皇を拝賀する奇妙な形式が大好きで、満足していた。天皇を拝むことが、自分自身の威厳を示し、又、自ら威厳を感じる手段でもあったのである。(「堕落論」『日本文化私観』講談社文芸文庫 pp.201-202)
坂口安吾の慧眼と博識が冴え渡る文章である。事実、藤原氏の摂関政治や、征夷大将軍による幕政などを鑑みれば明らかなように、日本史の様々な場面に見出されるのは「権威の形骸化」若しくは「権威と権力の乖離」という力学的現象であり、もっと卑俗な表現を用いるなら「本音と建前の使い分け」である。或いは極端な形式主義と看做しても恐らく大過はない。紛れもない究極の「権威」である「天皇」を推戴しつつ、その「権威」とは別個に存在する臣民の有力者が政治的実権を掌握し、水面下を暗躍して素知らぬ顔で物事を動かしていくという政治的様態は、例えば源氏の嫡流が途絶した後の「親王将軍」と「執権」との関係性にも明瞭に示されている。「権力」の中枢が、絶えず「権威」の物蔭に忍んで隠匿されるというのは、日本史の常道である。
こうした傾向を踏まえて眺めたとき、所謂「建武の新政」という改革を取り仕切った後醍醐天皇は、正に「異形の王権」(網野善彦)と呼ぶに相応しい人物である。森氏の叙述に従えば、後醍醐は「綸旨」の関わる分野を拡張し、軍事や恩賞を踏み込んで直轄し、裁判の処理にも自ら携るなど、積極的な「親政」を推進した異例の天皇であるということになる。言い換えれば、後醍醐において日本の政治的な「権威」と「権力」の合体が半ば腕尽くで実現されたのである。持明院統及び大覚寺統の間で争われた皇位を巡る鞘当ては代々、鎌倉幕府の意向と密接に結び付いた形で演じられてきた。後醍醐の幕府に対する敵対的な野心が、直接には大覚寺統の劣勢という時流や、大覚寺統の内紛に基づいて喚起されたのだとしても、重ねて蹶起を企てた後醍醐の独裁に対する信念は、そのような旧来の伝統そのものを破壊することに、そもそも強固な関心を寄せていたように思われる。
「権威」と「権力」を重ね合わせ、一体化することが、天皇の抱懐する野望の原則であるとするならば、両者を分裂させ、謂わば「権威」から「権力」だけを選択的に略取することは、藤原氏や将軍家など、人臣の頂点に位置する公卿や棟梁たちの有する野心の中核である。単純化して言えば、絶対的な王権としての天皇と、行政や司法に関する諸々の実務に携わる高位の人臣との間で演じる「権力」の苛烈な争奪が、日本史を貫き動かす巨大な伝統的活力なのである。
私は外国の歴史に関して日本史以上に無学文盲の輩であるから、この「権威/権力」の二重性という現象が本邦に固有の特徴であるのか、世界的に広く見られる傾向なのか、判断を下すことが出来ない。何れにせよ、天皇の帯びる絶対的な「権威」の正統性は明瞭に担保したまま、実質的な「権力」を骨抜きにして、臣下の筆頭が国政の実権を恣にするという構図は、年代を問わず、日本史において幾度も繰り返し発生している。「朝廷/幕府」の二重性は、鎌倉から幕末に至るまで、束の間の断絶を挟みながら数百年の長きに亘って維持されてきた。
後醍醐天皇は、幕府による容喙を排除して(その直接的な引鉄が、自らの皇位の脆弱性に由来したのだとしても)天皇による独裁的な親政を企図した。広範な分野に及ぶ政務の大半を自ら発する「綸旨」で決裁したのも、肥大した人臣による親政の歪曲や妨礙を警戒した為ではないかと思われる。それは国家における「権威/権力」の二重性を解消し、統合しようとする政治的衝迫の具体的表現である。但し、後醍醐の描いた野望は、日本史において極めて例外的な夢想であり、その実現は儚い寿命しか与えられなかった。建武の新政は瞬く間に瓦解し、足利尊氏による室町幕府の樹立が、旧来の「権威/権力」の二重性という国家的構造を恢復させた。つまり日本においては「権威/権力」の分裂こそ、国政における標準的状態であると言えるのかも知れない。実質を持たない虚飾、形式的な権威、そういったものを忠実に珍重しながら、具体的な行動の次元では、その崇高な権威を蹂躙して恥じない、そういう分裂的な心性が、本邦の歴史を通じて鮮明に浮かび上がるのである。天皇を権威に据えて征夷大将軍が実権を握り、征夷大将軍を権威に据えて執権が実権を握るという鎌倉期の入れ子構造、この無限の偏倚は、単なる偶発的な現象のようには思われない。絶えず「権力」を形骸化させながら、その残骸としての「権威」の外皮は決して廃絶しないという定型的な構図は、日本社会に内在する根深い傾向、或いは「宿痾」のように見える。こうした消息を指して、丸山眞男は「無責任の体系」という表現を持ち出したのだろうか。